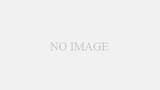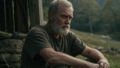現代社会では、毎日膨大な情報が流れています。ニュースサイト、SNS、友人の投稿、さらにはAIが生成する記事まで――私たちは一体何を信じればいいのでしょうか。フェイクニュースや偏った情報に振り回されて、なんとなく不安になることはありませんか?
実はこの問い、今から400年ほど前の哲学者、ルネ・デカルトも考えていた問題です。デカルトは「何を信じれば確実なのか」を徹底的に考え抜き、その答えを「我思う、ゆえに我あり」という言葉に託しました。今回は、デカルトの懐疑の思想を現代社会に引き寄せ、情報過多時代の思考法として活かす方法を考えてみましょう。
デカルト的懐疑とは何か
デカルトは、すべてを疑うことから哲学を始めました。五感も、経験も、他人の言葉も、完全には信頼できないと考えたのです。「もしかしたら、私たちは夢の中にいるだけかもしれない」とさえ疑いました。
しかし、そんな極端な疑いの中でも、デカルトが確実視していることがあります。それは「疑っている自分」が存在するということです。疑うこと自体が思考であり、思考している自分の存在は確実だと。これが有名な「我思う、ゆえに我あり」です。
現代社会にどう応用できるか
私たちの日常にも、デカルト的懐疑は応用できます。たとえばニュースやSNSで見かける情報に対してです。まずは一度立ち止まり、「本当に正しいのか?」と疑ってみることが大切です。情報源を確認したり、複数の意見を比較したりすることで、誤った情報に踊らされるリスクを減らせます。
また、アルゴリズムによって私たちの目に届く情報は偏ることがあります。気になるニュースや動画ばかりが表示され、知らず知らずのうちに偏った認知に陥ってしまう。そんなときも、デカルトの「まず疑う」姿勢が役立ちます。AIの回答も同様で、便利だからといって盲信せず、自分で考えてソースを確認する習慣が必要です。
デカルトから学ぶ「思考の手順」
デカルトは疑うだけでなく、物事を整理して考える方法も示しています。「方法序説」にある4つのルールは、現代人の情報整理にも活かせます。
- 疑わしいものはすべて疑う
SNSで「〇〇は危険」というニュースがあったとします。それをすぐに信じるのではなく、「その危険は条件付きなのか」「どういう条件なら危険にならないのか」などを考える。 - 問題を小さな部分に分ける
「この商品は本当に安全か」と考える場合、成分・製造元の情報・使用上の注意などに分けて順に確認していく。 - 簡単なものから順に解決する
まずは信頼できる一次情報を確認し、次に専門家の意見を調べる。そして最後に、自分の生活にどれくらい影響するのかを判断する。 - すべてを見直して確認する
調べた後も、少し時間を置いて「本当に正しい情報をもとに判断したか」「認識が違っていたり誤解しているところはないか」を再確認する。これにより、思考の抜け漏れを防ぐことができる。
この手順を意識することで、複雑で混乱しやすい情報社会でも、冷静に考え、正しい判断に近づくことができます。
結論
デカルト的懐疑は、決して「確かなものは何もない」とか「何も信じない」態度ではありません。「よりよく信じる」ための準備であり、現代社会ではむしろ必要な思考法です。情報に振り回されず、自分で考え、検証し、判断する力――それこそが、情報過多時代を生き抜くための最大の武器になります。
バズるために誇張したり、自作自演をしたりなど、事実とは異なるものが様々なところに溢れかえっています。疑わしいものに振り回されないようにしましょう。